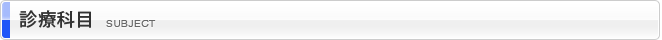稲田堤・京王稲田堤の内科・外科・胃腸科・肛門科「医療法人徳真会 西村クリニック」HOME > 禁煙外来・その他
アレルギー性鼻炎検査
≪検査≫
【鼻鏡検査】
通年性アレルギー性鼻炎では、下鼻甲介の蒼白・浮腫状腫脹・水様性鼻汁をみるが、
花粉症では赤色を呈する事も多い。
【アレルギー性の診断】
*鼻汁好酸球検査:鼻汁を採取染色し顕微鏡検査を行う。
(好酸球増多≒アレルギー性)
*血清総IgE検査・血中好酸球検査:
花粉症単独では、正常値の事が多い。
通年性アレルギー性鼻炎で高値となり、
喘息・アトピー性皮膚炎では更に高値となる。
【原因抗原の検査】
*皮膚テスト:スクラッチ(プリック)テスト
*血清特異的IgE抗体検査:Viewアレルギーなど
*粘膜誘発テスト:ハウスダスト・ブタクサのみ
≪その他の疾患≫
鼻汁好酸球検査のみ陽性の時→好酸球増多性鼻炎
全ての検査が陰性の時 →血管運動性鼻炎
との鑑別が必要になる。
季節性アレルギー性鼻炎(花粉症)
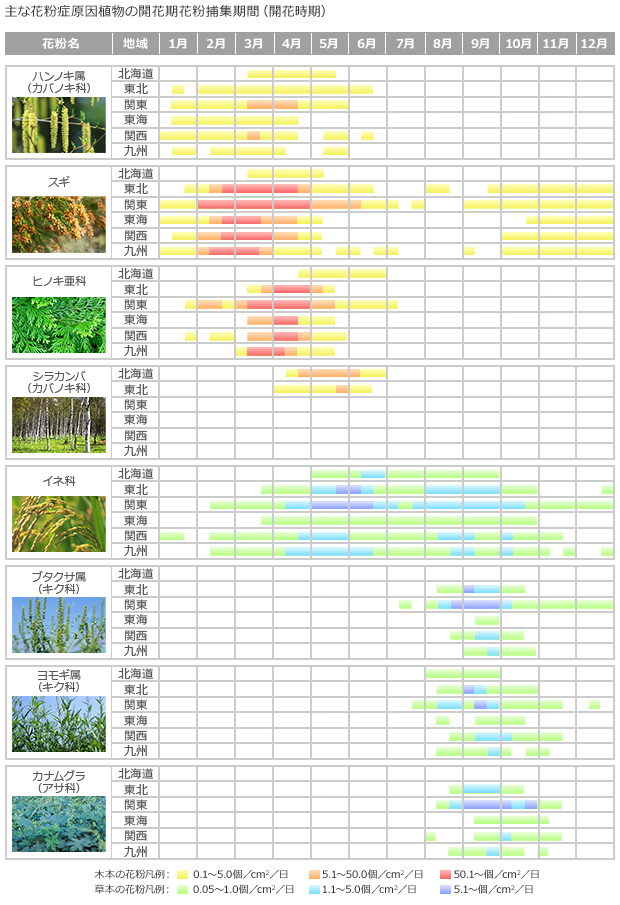
くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、
花粉飛散時期に症状が出現・増強するものが季節性アレルギー性鼻炎(≒花粉症)です。
花粉症では、生活圏における主な原因植物の開花時期を知る事が重要です。
*治療の第一歩は、抗原の除去と回避です。
①飛散の多い時の外出は控え、外出時には
マスク・眼鏡を使う。
②表面が毛羽だった毛織物などのコート等の使用
は避ける。
③帰宅時、衣服や髪をよく払ってから入室する。
洗顔・うがい・鼻をかむ。
④飛散の多い時の布団・洗濯物の外干しは
避ける。
⑤飛散の多い時は、窓・戸を閉めておく。換気時
の窓は小さく開け、短時間にとどめる。
⑥掃除を励行する。特に窓際を念入りに掃除
する。
*次にアレルギー性鼻炎治療薬による薬物療法です。
スギ花粉症の治療は、初期治療or導入療法を開始し維持療法を続ける。
≪第二世代抗ヒスタミン薬・抗ロイコトリエン薬・点鼻ステロイド薬≫による治療は、
【初期治療】
花粉飛散予測日または症状がでた時点から治療を開始する。
以前は飛散前からの服用を推奨される事もありましたが、最近の薬は即効性があり・効果も強く、
費用面からも飛散開始日or発症時から服用すればよいと思います。
但し、重症例は飛散予測日orその1週間前からの服用が推奨されます。
【導入療法】
症状が強くなってから治療を始める。
強めの治療から始め、症状軽減に合わせてstep downする。
【維持療法】
良くなった症状を維持するために、(初期治療薬)or(導入療法でstep downした薬)を花粉飛散終了まで続ける。
≪鼻アレルギー診療ガイドライン2016年版から≫
*抗ヒスタミン薬は、効果の強さ・眠気の出やすさ・服薬回数・食事の影響等から
患者様に適した薬剤を選択する事が可能です。
個人的には、重症例を除き発症日からの服用が良いと考えています。
*眼の症状が強い場合には、
抗ヒスタミン点眼薬・ケミカルメディエーター遊離抑制点眼薬を使用する。
(ステロイド点眼薬は、緑内障などの副作用があるので、慎重に使用する)
通年性アレルギー性鼻炎(ダニ・ハウスダストなど)
室内ダニの除去・回避は治療の基本として必ず行う
①掃除機がけは、吸引部をゆっくり動かし(1畳あたり30秒以上かける)、週に2回以上行う。
②布張りのソファー・カーペット・畳は出来るだけ止める。
③ベットのマット・布団・枕にダニを通さないカバーをかける。
④布団は週に2回以上干す。(困難な時は布団乾燥機で布団の湿気を減らす)週に1回以上掃除機をかける。
⑤部屋の湿度を50%、室温を20~25度に保つように努力する。
⑥フローリングなどの埃の立ちやすい場所は、拭き掃除の後に掃除機をかける。
⑦シーツ・布団カバーは、週に1回以上洗濯する。
薬物治療は、病型と重症度の組み合わせで選択する。
・第2世代抗ヒスタミン薬
・ロイコトリエン受容体拮抗薬
・鼻噴霧用ステロイド など、
アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法) ―スギ花粉・ダニ抗原に対する治療―
抗ヒスタミン薬等による
通常治療で十分な効果が得られない方にお勧めします。 但し、3~5年と長期間 毎日治療を行う必要があり、治療に即効性はありません。
また、花粉飛散時期(2~5月)には治療を開始する事はできません。
当院でも治療可能です。詳細については
こちらをご覧ください。
【手術】-鼻閉の改善目的-
鼻閉が保存的治療で改善されず、点鼻用血管収縮薬に対する反応性が悪いものが適応になる。
レーザー手術等:鼻粘膜表面を蒸散するもの・深層まで蒸散されるもの・粘膜を広く切除するもの
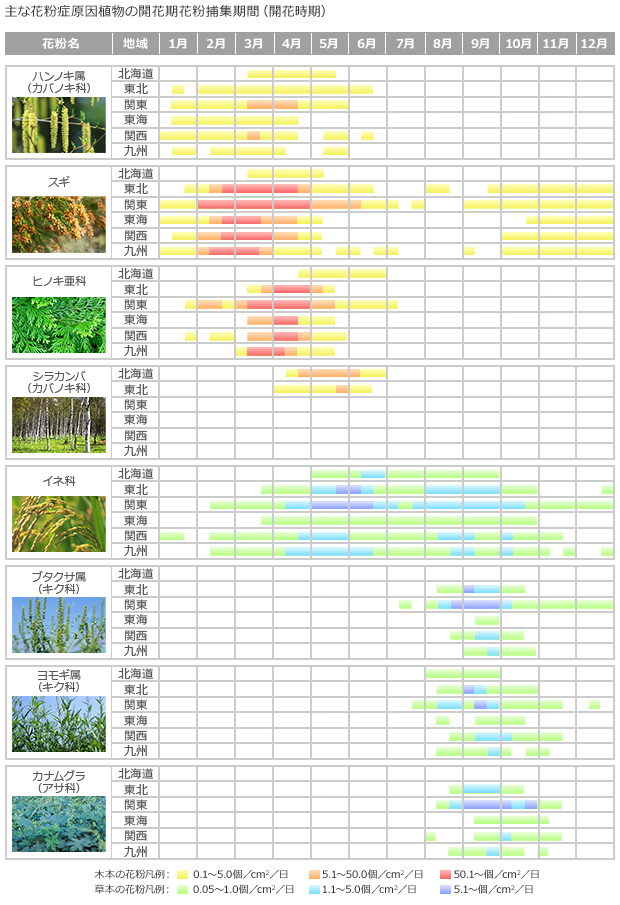 くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、
くしゃみ・(水様性)鼻汁・鼻閉を3主徴とするアレルギー性鼻炎のうち、